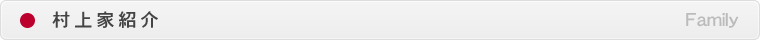村上 孝太郎 / 村上誠一郎の伯父
幻の財政硬直化打破キャンペーン 1/2
最初に荒波が押し寄せたのは、三木内閣の誕生からおよそ一ヵ月後の五十年一月六日のことだった。五十年度予算の大蔵原案内示から二日たったこの日、東京・大手町のパレスホテルで開かれた経済団体主催の新年祝賀パーティーに出席した三木首相は、年頭の挨拶のなかでつぎのような不満を漏らしたのである。
「私の内閣が発足したときには予算の骨格はすでにでき上がっており、限られた枠のなかで新内閣の特色を盛り込もうと努力したが、充分だったとはいえない。いまの予算は硬直化しており、新しい出直しが必要だ。予算編成の方式に根本的な改革を加えなければならない」
大平蔵相を筆頭とする財政当局への痛烈な非難だった。三木がここで問題にした財政の硬直化というのは、予算編成が官僚主導で進められ、最高権力者といえども思いどおりにならない実態を指していた。政権担当後、老齢福祉年金のアップなど、持論の福祉政策を大胆に実現しようとして期待どおりの成果が上がらなかったのは、既得権の積み上げ方式という従来の予算編成が問題であると判断したのだろう。硬直化を打開しないことには首相主導の予算づくりは不可能と思い込んだ三木は、それからしばらくのあいだ、ことあるごとに 「硬直化打破」 を叫び、大平蔵相を始め財政当局にも執拗にその具体策の検討を指示し続けた。
財政の硬直化という問題は何も三木首相によって初めて持ち出されたテーマではなかった。昭和四十年代初めから折に触れて議論の的となってきた課題だったが、この問題が最初にスポットライトを浴びたのはその約七年前の佐藤内閣時代のことであった。いまもなお大蔵省関係者のあいだで語り草となっている 「財政硬直化打破キャンペーン」 という動きがそれで、四十三年度の予算編成を前にして四十二年 ( 一九六七年 ) 秋から翌年の初頭にかけて、大蔵省内だけでなく霞が関・永田町の一帯を揺り動かすほどの一大旋風を巻き起こしたのであった。
キャンペーンの始まりは四十二年九月十四日のことで、この日の午後、大蔵省の谷村裕事務次官 ( 元東京証券取引所理事長。現東京証券計算センター社長 ) と主計局長の村上孝太郎 ( のち事務次官を経て参議院議員。故人 ) とが首相官邸に当時の佐藤首相を訪ね、「義務的な当然増経費で財政が硬直化している。これを放置すればいずれ国家財政が破綻する」 と直訴したことから騒動の幕が切って落とされた。これを契機に谷村や村上は自民党の有力政治家に片っ端から波状攻撃を仕掛けていった。幹事長だった福田赳夫、政調会長の西村直己 ( 元農相。故人 ) 、それに当時、派閥の領袖だった前尾繁三郎 ( 元衆議院議長。故人 ) 、藤山愛一郎 ( 元外相 ) などのもとに出向いて、財政危機の到来が近いことを訴え続けた。
だが、そのころは現代とは違ってまだ高度成長経済の真っ盛りで、財源には相当の余裕があった時代である。予算編成の時期になると、各省庁は要求の満額獲得に秘策を練っていたし、政治家のほうも翌四十三年夏の参議院選挙を控えて予算の分捕りに血眼になっていた。そんな時代にいきなり大蔵省が硬直化打破の狼煙を上げたのだから、官僚や政治家たちは仰天し、同時に大蔵省の狙いをあれこれと詮索した。谷村や村上から話を聞かされた政治家の多くも、大蔵省の主張を、四十三年度の予算編成を抑制型のものにするための先制攻撃ではないかと受け止め、硬直化打破という言い分に対して眉に唾する連中が少なくなかったのである。
ところが、大蔵省側は本気だった。その一年半前の四十一年一月、当時の蔵相、福田赳夫の手によって戦後初めて国債が発行され、日本の財政は二十四年 ( 一九四九年 ) ドッジ・ライン以後、十七年のあいだ続けてきた均衡主義に別れを告げていたが、谷村や村上は、公債を抱いた財政という新しい状況のもとで従来のような予算編成を続けていると、ずるずると国債依存の財政運営に引きずり込まれ、そのうちに借金地獄の泥沼にはまってしまうという危機感を募らせていたのであった。
- 次のページへ »